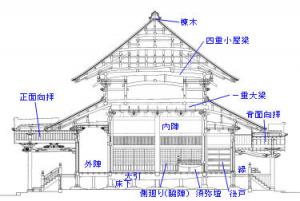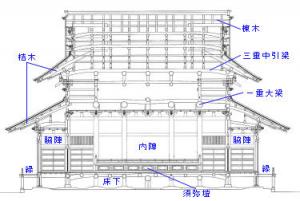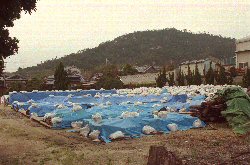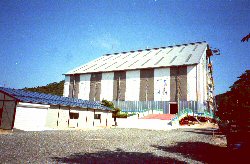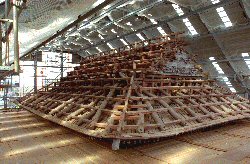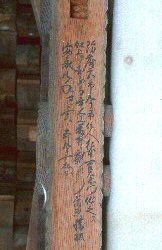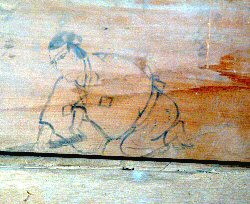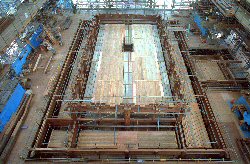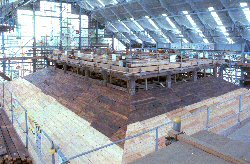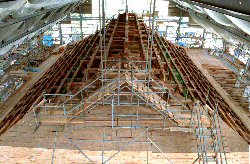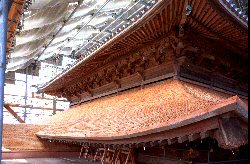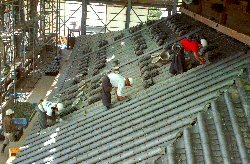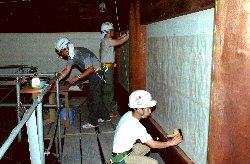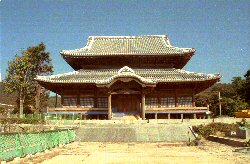本文
周防国分寺金堂平成の大修理
周防国分寺金堂平成の大修理
解体
天平の甍 名称:重要文化財国分寺金堂保存修理事業 |
金堂 |
梁間断面図 |
桁行断面図 |
構造と規模
本瓦葺二重入母屋(いりもや)造、桁行7間(約22m)、梁間4間(約16m)、高さ約18m
正背面向拝一間唐破風からはふ)造
修理前正面(平成9年) |
瓦の解体(平成9年11月) るところ。瓦は土居葺の上に土をのせて葺かれている。 |
瓦置き場(平成9年) |
素屋根建設(平成10年8月) |
上層屋根野垂木(平成10年12月) |
上層屋根小屋組(平成11年1月) |
上層上部小屋組解体(平成11年2月) |
上層軒の解体(平成11年3月) |
組物解体(平成11年4月) |
下層屋根野垂木(平成11年5月) |
桔木(平成11年6月) |
下層軒回り(平成11年6月) |
一重大梁(平成11年7月) |
下層組物(平成11年8月) |
内陣天井格縁(ごうぶち)(平成11年9月) |
内陣丸柱(平成11年10月) |
床廻り(平成11年11月) |
礎石と調査(平成12年1月) |
墨書 |
落書 |
基壇せん積み |
写真図面提供:財団法人文化財建造物保存技術協会
組立
新材の加工(平成12年7月) |
部材の補修 |
床下叩き(平成12年12月) |
立柱安全祈願(平成13年1月) |
内陣軸部組立(平成13年2月) |
内陣組物完了(平成13年4月) |
内陣組立完了(平成13年5月) |
正面向拝(平成13年5月) |
下層軒工事(平成13年7月) |
下層軒回り組立(平成13年8月) |
下層桔木組立(平成13年9月) |
下層桔木(平成13年9月) |
下層母屋組立(平成13年10月) |
下層野地板(平成13年11月) |
上層組物(平成13年11月) |
上層組立(平成13年12月) |
上層軒化粧裏板(平成14年1月) |
五重小屋梁組立完了(平成14年2月) |
上層組立完了(平成14年4月) |
上層屋根野垂木組立完了(平成14年4月) |
上棟式(平成14年5月) |
上層屋根土居葺(平成14年7月) |
上層屋根平葺完了(平成14年7月) |
上層屋根丸瓦葺完了(平成14年9月) |
上層妻部屋根縁(平成14年9月) |
縁高欄組立(平成14年11月) |
上層瓦の目地漆喰(平成14年11月) |
大棟目地漆喰(平成14年11月) |
上層屋根完成(平成14年11月) |
上層軒下部の組物(平成15年1月) |
下層屋根の土留桟 |
下層屋根瓦葺(平成15年4月) |
下層屋根の目地漆喰(平成15年6月) |
内陣後背の壁紙下貼り(平成15年7月) |
正面向拝完了(平成15年8月) |
風鐸新規作製(平成15年1月) |
床下木組 |
素屋解体(平成15年9月) |
ほぼ完成した金堂(平成15年10月) |
落慶法要 |
写真提供:財団法人文化財建造物保存技術協会